『赤ちゃんの死へのまなざし ―両親の体験談から学ぶ周産期のグリーフケア(竹内正人/編著、井上文子・井上修一・長谷川充子著)』という本を手にしました。
この本は、「赤ちゃんの死」死産を経験した井上さん夫婦の体験談を中心に、産科・医療現場・そしてその後のケアのあり方について語られています。
当事者の井上さんの悲しみだけでなく、夫や医療者の葛藤も描かれていて、
「どう寄り添えばよかったのか」を考えるきっかけを示してくれています。
赤ちゃんを亡くしたご家族にも、医療に携わる方にも、
ぜひ手に取ってもらいたい一冊です。
知らなかった医療者のまなざし
特に印象的だったのは、医療者側の視点が丁寧に描かれていたこと。
「どう寄り添えばよかったのか」「言葉を失ったとき、どうすればよかったのか」
そんな葛藤や迷いも綴られていて、読むうちに自身の経験と重なって胸が締めつけられながらも、
“悲しみを分かち合おうとする人の存在”に救われるような感覚がありました。
『赤ちゃんの死へのまなざし』は、死産を経験された方が
「その時、何が起こり、何を感じたのか」を丁寧に綴った一冊です。
読み進めるたびに胸が締めつけられ、
そして同時に「私も同じだった」と共鳴する瞬間が何度もありました。
赤ちゃんを冷たくしてしまった後悔
お別れの前の日、井上さんは「赤ちゃんをきれいなままで見送りたい」と、
葬儀社のすすめで冷蔵庫に寝かせたそうです。
翌日、すっかり冷たくなったわが子を抱いた瞬間、
「可哀想なことをした」と感じたと書かれています。
私も同じような経験があります。
退院後、真夏だったのでそらを自宅の冷蔵庫に入れていた時間がありました。
「こんな冷たい場所に閉じ込めてしまってごめんね」と、申し訳なさがありました。
ただそらの体は冷たくなってしまったけれど、最期までふわふわで柔らかかったのを覚えています。
きっとどうするのが正解、なんてない。ただそれがあの時の自分にできる、精一杯の“愛し方”でした。
綺麗なままで保ってあげたい、それもわが子を想う愛情なんだよ、大丈夫だよ、と後悔するすべての親にそう声を掛けてあげたいです。
「亡くなった赤ちゃんも、同じように扱ってほしい」
心に強く残った言葉があります。
「亡くなった赤ちゃんであっても、元気に生まれた赤ちゃんと同じように扱われるのが一番良いのではないか」
まさにその通りだと思いました。
病院でふかふかのコットに寝かせてもらって、
「頑張ったね」「おめでとう」と声をかけてもらえること。
それだけで、どれだけ救われただろうと思います。
現実との落差と、非現実感
井上さんが「喪服を買いに行ったら、隣の売り場はベビー用品だった」と書かれていて、思わず涙がこみ上げました。
私も、そらの棺に入れるおもちゃや服を買いに行ったとき、幸せそうな妊婦さんや家族連れを見て、「どうしてこんなに違うんだろう」と悲しくてたまらなかった経験があります。
また「私は本当に妊娠していたのだろうか」と感じる非現実感も、まさに今の私と同じです。
あの半年間が、夢のように遠く感じてしまう。
でも、この本を通して「同じ思いをした人がいる」と知れたことが、少し心を軽くしてくれました。
「おめでとう」の言葉がもたらす救い
病院スタッフからかけられた「おめでとう」の言葉が嬉しかった、という井上さんの言葉にも強く共感しました。
「おめでとう」は、生まれてきた命そのものへの祝福。
亡くなってしまったとしても、
確かに“この世に生まれた”という事実を肯定してくれる言葉なんですよね。
関わる医療者の方々へ
死産や流産のケアは、当事者によって感じ方差が違い、一律にマニュアル化することはできないと思います。
ただ、突然の宣告を受け、茫然とするしかない家族に対して、「これからどのようなプロセスを踏んでいくのか」落ち着いて教えてくれる存在がいてくれることはありがらいです。
そしてその際に決してルーチン業務のように事務的に行わないでほしい。
私自身、悲しみに寄り添ってくれるスタッフさんに出会えた一方で、
事務的な対応に心が追いつかず、悲しい思いをした場面もありました。
沐浴、手形、写真撮影――
触れ合いの時間を設けてもらえたことはとても良かったのですが、わが子との最後の時間を“作業”として扱われるのは、とても辛かったです。
本の中で、担当助産師さんがこう語っています。
「どうしたら後悔させないだろう」「私は事務的になっていないだろうか」
——その姿勢こそ、私たち家族が最も求めている優しさなのだと思います。
編者である竹内先生はこう述べています。
「生きて生まれた子と同じように接してほしい。
両親にとっては亡くなっていたとしても大切な赤ちゃんなんです。」
医療には限界がある。
どんなに発達しても、命を完全に救うことはできない。
でも「寄り添う心」には限界なんてない——
この本を読みながら、改めてそう感じました。
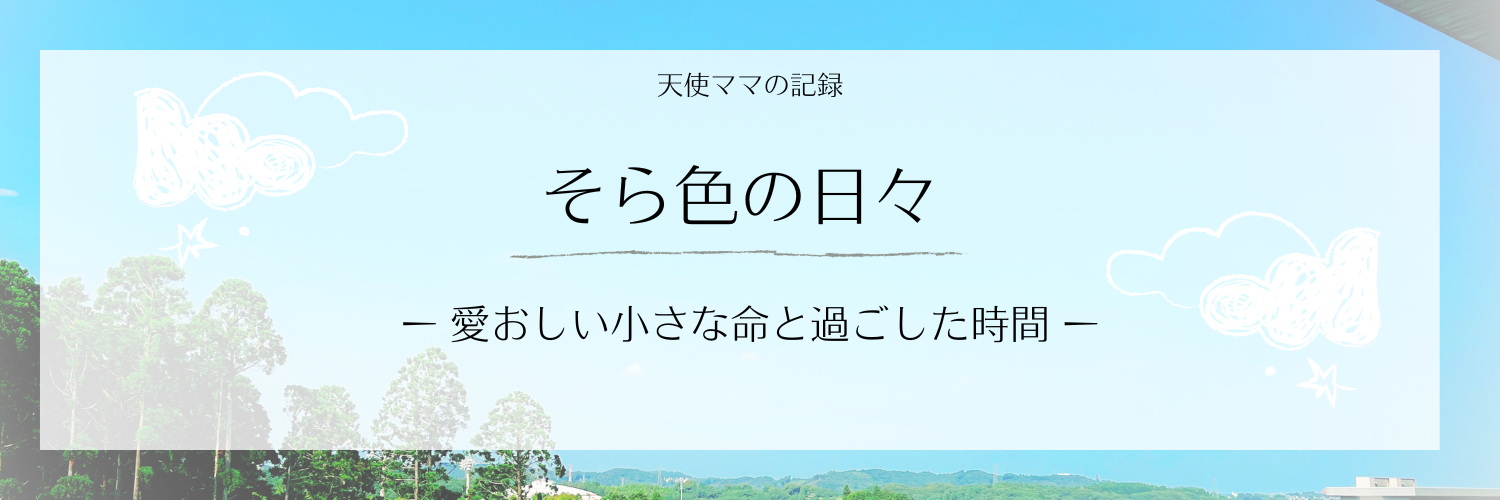
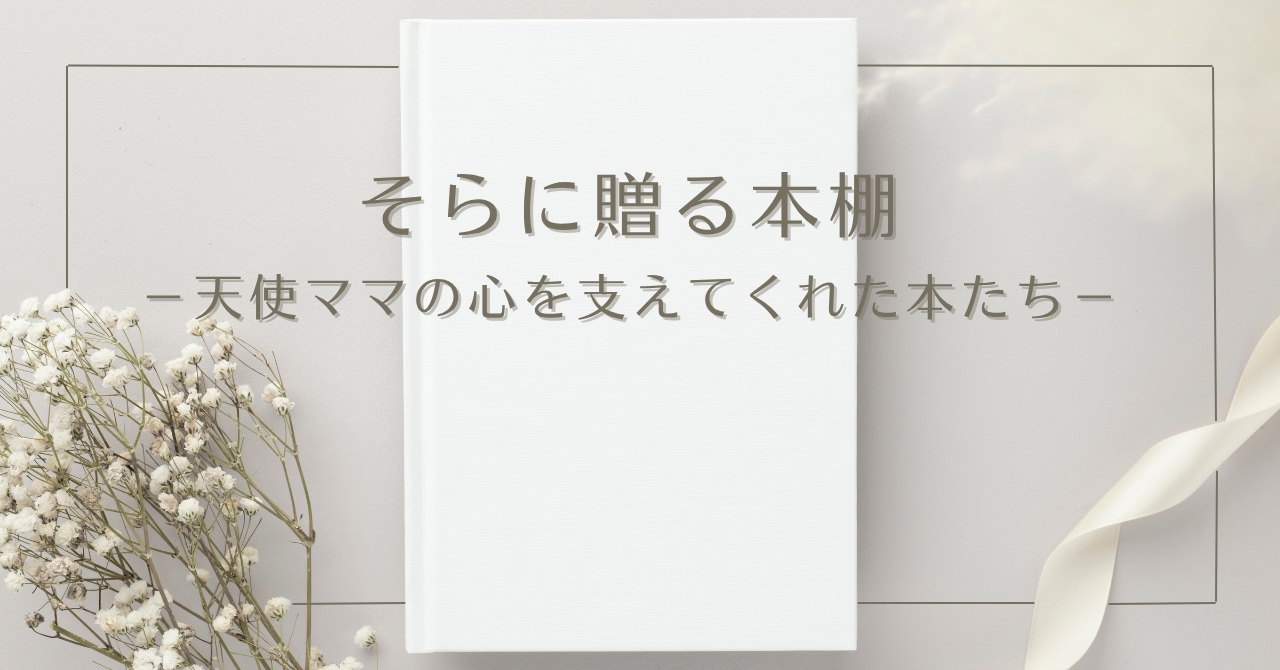

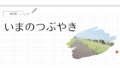
コメント